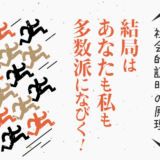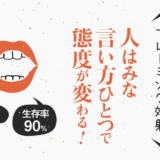京セラ創業者 稲盛和夫のシンプル思考
稲盛和夫(1932-2022) 京セラ、第二電電(現・KDDI)創業者、日本航空取締役名誉会長
バカな奴は単純なことを複雑に考える
普通の奴は複雑なことを複雑に考える
賢い奴は複雑なことを単純に考える
稲盛和夫に心酔するSBIホールディングスのCEO 北尾義孝(1951-)は、このことばの本質を「賢い奴は複雑なことのポイントが直感的に分かる」ということであると分析しています。
サイゼリヤ創業者 正垣泰彦の繁盛哲学
サイゼリヤ創業者 正垣泰彦(1946-)
おいしいから売れるのではない
売れているのがおいしい料理だ
顧客の期待値を超えた価値を提供することで、大学在学中に開業した一軒のお店『サイゼリヤ』を、全国チェーンに拡大した正垣泰彦の事業に対する確信が、このことばに凝縮されています。
井深大 1兆円企業SONYの原点
ソニー創業者 井深大(1908-1997)
難しいからこそやる価値がある
井深大は「お宅のような小さな会社がアメリカでも作れないトランジスタラジオを作るなんて無理だ」という意見が大勢を占める中、井深と盛田昭夫はトランジスタラジオの開発を決意します。
永谷園 永谷嘉男の『小』が『大』に勝つ法
永谷嘉男(1923-2005) 永谷園創業者
小規模な企業が生き残るには、局地戦に勝て
コロナ禍で、働き方が大きく変化しました。今から40年前に永谷園は、斬新な”働き方“制度を導入し、大ヒット商品を生み出しました。
永谷嘉男は、“ご飯のお供”というニッチなジャンルを狙い、局地戦を展開し『お茶漬け海苔』、『あさげ』、『すし太郎』などのヒット商品で食品市場に独自の地位を築きます。
日本電産 永守重信の“ナンバー1”への情熱
永守重信(1944-) 日本電産代表取締役会長CEO
1番以外は、全部ビリ
永守重信は1973年、28歳の時に、京都で3人の仲間とともに2台の設備で自宅の納屋で起業し、世界一のシェアを獲得した永守重信。激しい競争に打ち勝つために「1番」にこだわり続けます。
信越化学 金川千尋が説く2つのリスク
金川千尋(1926-2023) 信越化学工業代表取締役会長
リスクには「踏んではいけないリスク」と
「踏まざるを得ないリスク」の二つがある
政情不安や通貨不安、敵対的買収の実施、株や土地などへの投資といった企業にとって致命傷に成りかねないリスクと、リスクを恐れて好機を逃したら勝てないビジネスがあると言います。
小売の神様 セブンイレブン 鈴木敏文の価格哲学
鈴木敏文(1932-) セブンイレブン、セブン銀行設立者、セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問
低価格は価値の一要素にすぎない
モノを仕入れて販売する小売業では価格は価値を作る一要素です。顧客が定価で売っているコンビニで買ってしまうのは、コンビニが便利だからです。便利さに価値を感じて人は定価でも買うのです。いくら値引きしても価値を感じなくては、買ってもらえません。
商社界の鬼 伊藤忠商事 越後正一の勇気
越後正一(1901-1991) 伊藤忠商事 第5代社長
成功は窮苦の間に芽生えており、
失敗は得意満面の間に宿る。
黒雲のうしろには、太陽が輝いている
逆境を次々と新たなチャンスに変え伊藤忠商事を世界的総合商社に導いた越後正一。世界恐慌、一寸先は闇の繊維相場での修羅場の経験に裏打ちされた“商社界の鬼”の名言です。
社長就任から10年。1971年8月15日、アメリカ大統領 リチャード・ニクソンが、金とアメリカ・ドルの交換停止を突然発表した「ドル・ショック」に動揺する社員に送ったメッセージです。
コピー機で日本のオフィスを変えた市村清の信念
市村清(1900-1968) リコー三愛グループ創始者
利己ではなく、利他なのだ。
自分が売ってくるのはたかが知れている。
多くのお客さんがセールスマンになってくれなければ、
どうして他人以上の売上ができようか。
そうすれば、儲けようとしなくても、自然に儲かるようになる。
200を超す企業を創業したイノベーター 市村清。1955年に複写機リコピー101を発売し、日本のオフィスの事務作業を大きく変えます。コピー機の複写のようにお客様を増やす秘訣は利他の精神です。
稲盛和夫『生き方』(サンマーク出版)
稲盛和夫『考え方』(大和書房)
正垣泰彦『おいしいから売れるのではない 売れているのが おいしい料理だ』(日経BP)
井深大『井深大 自由闊達にして愉快なる 私の履歴書』(日本経済新聞出版)
金川千尋『私の履歴書 毎日が自分との戦い』(日本経済新聞社)
鈴木敏文『朝令暮改の発想 仕事の壁を突破する95の直言』 新潮社
![東京マケノモン新聞[WEB版]](https://makenomon.jp/wp-content/uploads/2019/11/logo191117.png)